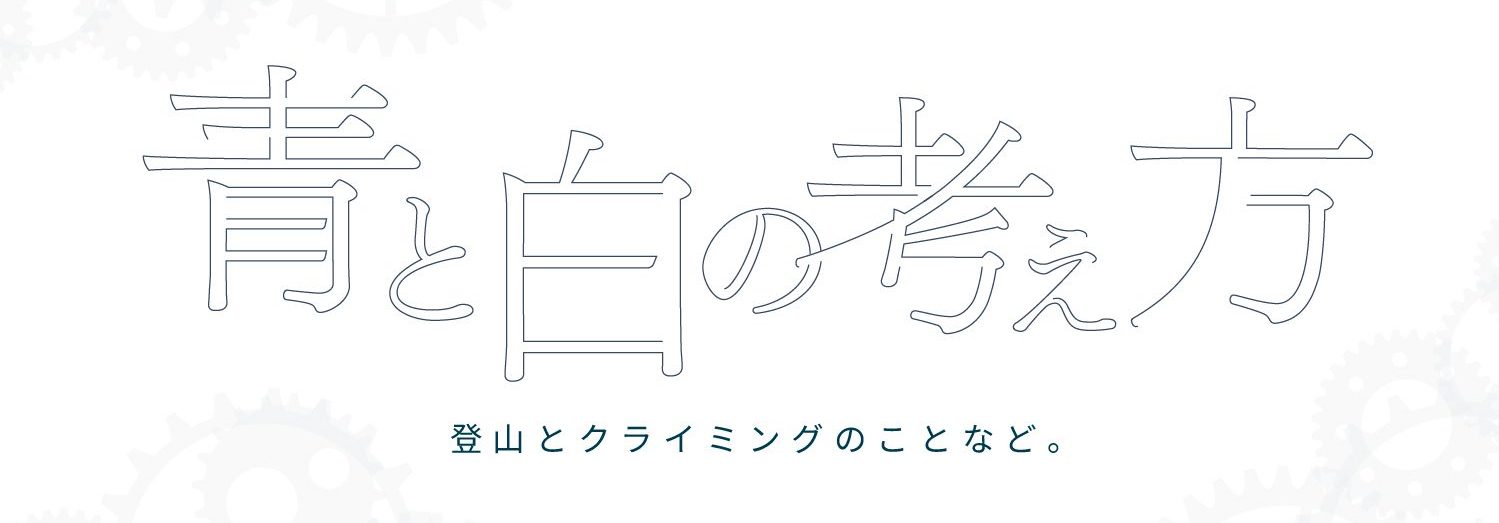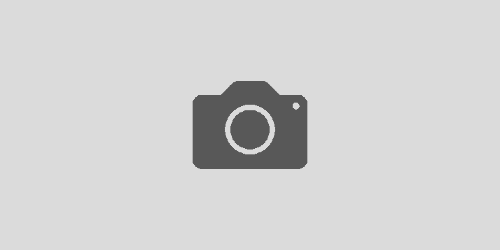JFAリボルト職人検定講習 (2019-10-05〜06)
2019年10月5~6日に、備中はリバーパークで行われた日本フリークライミング協会(JFA)主催のリボルト職人検定講習に参加しました。これまで、公開されている情報を自分なりに調べて、ハンマドリルを購入して施工トレーニングをしていましたが、その方法で正しいのか不安に感じていました。今回の検定講習に参加することで、独学ではとうてい辿りつけなかった多くのノウハウを短期間で得ることができ、とても勉強になりました。自分なりに消化するため、学んだポイントを振り返って記録します。
1日目 実技 09:30-16:00
ボルトを打つ位置の決め方
- 岩の見た目がボロボロでなくフラットな所。
- 壁の際から150mm以上は離す。
- ハンマーで叩いて(打診して)、岩が浮いていないかを確認する。浮いているとポコポコと音がする。
- ハンマーによって音の鳴り方が変わる。沢登り用の軽量モデルだとキンキンと高い音がするので、打診には不向き。ペツルのタムタムが良い。
既設ボルトの状態
- まずは材質を見極める。スチールかステンレスか、それともアルミなのか。
- 施工方法を見極める。カットアンカー、オールアンカー、全ネジボルト。
- スポーツクライミングの支点強度は25kN以上。
- RCCボルトやリングボルトは穴底にチップが当たって拡張する仕組みなので、ちょっと浅打ちくらいの方が良く効いていることが多い。逆に、奥深くまで刺さっていると、十分にチップが拡張されていない可能性がある。
施工方法の選択
- グージョンボルト(ウェッジ式アンカー)の頭が飛び出しているのは、岩が柔らかく効きが甘いため。このような場合はケミカルアンカーに打ち替える。
- 石灰岩や凝灰岩などの堆積岩系は、基本的にケミカルアンカーで施工する。花崗岩のように硬い岩はウェッジ式アンカーで良いとされてきたものの、岩の風化が進んで脆くなって支持力が十分でない例が出てきている。小川山では、ウェッジ式アンカーをペンチで引張っただけで抜けた例もある。
- この岩にはこの方法、という固定観念にとらわれず、常に新しい考え方を取り入れる姿勢が大切。
- ケミカルアンカーは壁面に対して15°下向きになるようにセットする。
- ラッペルステーションは下側のボルト位置を先に決める。カラビナをかけて問題なく使える位置にする。上側は下のボルトの垂直線と約30°ずらすのがベストポジション。
装備
- ハンマドリルはスリングで肩にたすき掛けしておけば、そのまま使える。
- ハーネスにマグネットを付けておくと、ハンマーを一時的に固定できて便利。
- ハンマドリルの回転スイッチは中間にしておくとロックがかかる。使わないときには中間にしておくこと。
- 使用直後のビットは熱いので火傷に注意。
ウェッジ式アンカーの施工
- 岩面に対して垂直にドリリングする。これは全ネジボルトでも同じ。
- ボルトの全長以上にドリリングしておけば、失敗したときにボルトごと埋め込めることができる。
- 締め込んだ際に2山残るのが規定の長さ。
- テーパ部がずれることで拡張するという特性上、効きが締め込み強さでダイレクトに確認できるのが特徴。
- ドリリング時は、途中で少し力を抜く瞬間を設ける。粉を出すため。ビットをすべて抜く必要はない。
- フルストロークでのブロワーとブラッシングを最低3セット行う。ブラッシング時にブラシに岩の粉が着くので小まめに叩いてクリーニングする。
- ウェッジ式アンカーにハンガーとナットを取り付けた状態(ナットはツライチ)でグージョンボルトを打ち込む。奥に入りすぎないようにするためと、ネジ山を潰さないため。
ウェッジ式アンカーの引抜き
- ウェッジ式アンカーの下にφ12mmビットで穴あけする。深さは埋まっているアンカーの長さ以上。雪だるま状の穴が空いた状態なので、雪だるまの首の部分を広げるために、φ5mmビットでスイングしながら加工する。
- その状態でウェッジ式アンカーをハンマーで下向きに叩き、左右に叩き、緩んできたらバイスプライヤで引き抜く。
ケミカルアンカーの施工
- グルーにはHILTYのRE500(ピンク)、HY200R(グレー)が良く用いられる。基本的には強度が高いRE500を用いる。RE500は濡れた状態でも使用可能。HY200Rは短時間で硬化する。HY200Aというのもあり、こちらは本当に即座に硬化する。
- 旭化成のケミカルアンプルも水洗いした方が良い。掃除が不十分だと抜けてしまうことがある。抜けた実例は1件あり。
- ウェッジ式アンカーを抜いた穴に、下向き15°になるよう改めてドリリングする。最初は角度がつきにくいので力を込める。ビットの山がなくなるあたりまで掘るとちょうどよい深さになる。
- ケミカルアンカーの溶接部が上側になるようにする。深さは、内側の溶接部が岩とツライチになる程度がベスト。
- ケミカルアンカーが12時の位置になるよう、上側を掘る。下から上にえぐるようにする。
- Nさんは、少し離れた位置に浅い穴を空け、そこから下向きにえぐるとのこと。なお、被った位置であれば、10mmビットを使い、ハンマーではめ込むと固定できる。
- グルーガンは袋に入った2液1セットをケースに詰め、さらにそのケースをヒンジ状にはめ込んだあと、全体をカパッとはめ込む。トリガーを2回ほど押すと固定される。
- 最初の利用では3回分を空打ちする。打った後は圧解除の黒ボタンを押さなければタレ流しされ続けてしまう。
- 25-29℃では20min以内に施工し、施工後3.5hは動かさないようにする。
- 乾式で掃除後、水でも掃除。水は蓋に小穴を空けたペットボトル。ブラシは乾式と湿式で別々にする。
1日目 座学 18:30-21:00
夕食後に座学。テキストに従って要点をIさんが説明し、質疑応答を挟んで進められた。装備、材質、JFAの活動、リボルト職人のランク等。
- クライミングは本来自己責任であり、ボルトがプロテクションとして有効かどうかは本来クライマーそれぞれが見極めることであり、ボルト施工者に責任はないはずだけれど、近年はそうはいってもいられない。リボルトした人間が法的に責任を追求されることもある。
- ケミカルガンの圧抜きを忘れると、ケミカルが垂れてきて、皮膚に直接触れると火傷することがある(ケミカルが硬化する際の化学反応で発熱する)。そのため、皮膚が露出しない服装にする。特に足首が露出しないよう注意。
- ケミカルガンのノズルが固まっているのに、無理やりトリガーを引いて圧をかけると、ケミカルの袋が破れることがある。1つだけ破れてしまうと混合比が変わって硬化しなくなってしまう。
- クイックリンク(マイロン等)は、安全環が下側になる様に設置する。逆だと、振動で安全環が緩んだときに開いてしまうことがある。これは通常の環付カラビナでも同様。
- ステンレス鋼は熱膨張率が大きいため、ナットを締める際に焼付きしやすいので注意。CRCで潤滑すると良い。
最後に明日のリボルトのチーム分けをして、 1日目は終了。
2日目 リボルト 9:00-16:00
いよいよ実際のルートのリボルト。講習生3人1組でチームを構成し、各チームに1人決められたリーダーの指揮の基、協力してリボルトを実施する。それぞれのチームには特Aクラスのリボルト職人が1人ずつ付き、不安に思ったことはすぐに確認できるし、怪しい内容で作業しようとすると即座に修正いただける状態。
僕らのチームは、向かって右の2ルートを整備した。リボルト対象となるのは、ステンレス鋼製のM10オールアンカーにステンレス鋼製のハンガーというもの。すごく錆びていたり施工が悪かったりする訳ではないけれど、施工後20年近く経とうとしていることから、Fixe PLXケミカルアンカー+HILTY RE500グルーという現在最高品質のボルトに変更する。
リボルト手順
- 対象ルートを登り、既存終了点にラビットノットでロープをフィックスする。
- フィックスロープをユマーリングして、既存終了点の近くに新たな終了点を設置する。全ネジボルトをケミカルアンプルで施工し、ラッペルステーションを設置。まずは穴開けと洗浄。
- 洗浄した部分が乾くのを待つ間、下から順に中間支点をリボルトする。基本的には、現在のボルト位置にケミカルアンカーを設置する。
終了点の穴あけ
終了点クリップに不自然でない部分に新しい終了点を設置すべく、既存終了点のやや左、岩が浮いていないことを確認してドリリング。しかし、50mmくらい掘り進めたところで急にドリルがスコッと奥に入った。明らかに奥に空洞がある。見守ってくれていたKさんも、これはダメだみたいなリアクション。
仕切り直すべく、ハンマーで辺りの岩を打診し、1段下の岩面に設置することに変更。ラッペルステーションを合わせながら位置決めし、慎重にドリリング。今度は大丈夫そうだけれど、岩面に対して前後左右ともに垂直に穴あけするのはとても難しく、右にずれてるよ、などKさんに指摘されつつ、なんとか1つ目の穴を施工した。
ラッペルステーションを仮止めし、左上の穴を位置決めする。このとき、ラッペルリングにテンションがかかった際に2つのハンガーに均等に荷重されるようにするのがポイント。なかなか難しい。2つ目の穴空けも無事終了。
今度はそれぞれの穴をブラッシングする。まずは水なしで、ブロワーとブラシを3セット。続いて、水洗いとブラシとブロワーを3セット。蓋に穴を空けた500mlペットボトルから水を出して洗浄。ブロワーで水ごと汚れを吹き飛ばすのがポイントのようだ。一通り掃除が終わったら、水が乾くのを待つ。
中間支点のリボルト
既存の中間支点が設置されている岩の強度に問題がなさそうなら、そのままケミカルアンカーに打ち替える。まずはハンガーを撤去する。昨日練習したとおり、オールアンカーの真下に12mmビットで穴空けし、5mmビットで雪だるまの首部分を広げる。岩の削りカスをブロワーで吐き出し、ハンマーで上下と前後に叩いてこじっていれば徐々にテンションが抜けて動いてくるので、頃合いを見てバイスプライヤーで掴んで引っこ抜く。
抜いて出来た穴にケミカルアンカーを設置するため、15°の角度を付けてドリリング。ケミカルアンカーの座りがよくなるように上側をドリルでハツり、微調整をしたら水洗いでブラッシング。
この一連の作業を中間支点の数だけ繰返すのだけれど、場所によってはフィックスロープから微妙に離れてしまって、無理な体勢になったりと難しい。また、ケミカルアンカーを施工する角度(ドリリングの角度、ハツリの角度)は、壁にいる本人からは分かりにくいので、地上にいる第三者に見てもらうのが確実。実際にクイックドローをかけて、干渉しないかを確認しておく。
古いボルトの抜き取りと、ケミカルアンカー設置穴の準備ができたら、下から順番にグルーを注入しケミカルアンカーを設置していく。奥の方からゆっくりとグルーを穴に詰め、満タン少し手前で止める。グルーガンの圧を抜くボタンを押し忘れないように注意する。ケミカルアンカーを回転させながら奥まで差し込む。
ケミカルアンカーの溶接部のあたりまでグルーに埋まるようにしておく(乾燥後、もしもケミカルアンカーが抜けてきたら、グルーが割れるので異常が分かる)。ヘラでグルーをなるべくフラットになるよう整えて設置終了。
終了点(ラッペルステーション)の設置
穴を空けて、ケミカルアンプルで全ネジ施工したボルトに、ラッペルステーションをセットしてナットを本締めしているときに異常は発覚した。2本のボルトのうち、下側のボルトを締めていたら、いつまでたってもテンションがかからず、ナットを締める度に全ネジボルトが抜け出てきた。
これは、内部に空洞があって、ケミカルアンプル1本分では体積が足らず、全ネジボルトを固定できていなかったことによる。下にリボルト指導員のIさんとKさんがいたのですぐさま指示を仰ぎ、全ネジボルトをケミカルグルーで施工し直すことになった。
ナットを回して全ネジボルトを抜き、もう一度ドリリングする。そして入念に掃除。ケミカルグルーはRE500であれば水に濡れた状態でも施工できるけれど、硬化完了まで時間がかかりすぎる。そのため、効果時間の短いRE200Rで施工する。RE200Rは水滴が着いた状態での施工はできないので、ブロワーで必死に、入念に、これでもかと乾燥させる。乾燥したら、下からグルーガンを上げてもらい、内部の空洞に行き渡るようたっぷりと注入し、全ネジボルトを施工。
硬化時間は1時間。その間、隣のルート整備や撤収の準備などを進める。硬化後、チームリーダがラッペルステーションを本締めし、今度はしっかりセットできたので一安心。併せて、古い終了点のハンガーを外して、終了点に使用されていたオールアンカーはディスクグラインダでカット。これにて一連のリボルト作業が終了した。
感想
一流になりたければ一流に交われという言葉がありますが、リボルトにおいて間違いなく日本一の講習を受け、一流の仕事を目の当たりにできました。普段何気なく登っている岩場の安全は、(クライマー全体の数からすれば)ごく少数の方々の尽力によって保たれていることを身を持って知りました。
僕は、3人チームでやっと2ルートをリボルトしたのみですが、疲れ方は尋常ではありませんでした。今回ご一緒させていただいた講師やサポートの方々と受講生の方々、TCNetの方々に感謝いたします。どうもありがとうございました。
これでJFA公認リボルト職人に仲間入りできました。スポーツクライミングの高グレードは登れませんが、マルチピッチ系の岩場等で、なんらかの貢献ができればと思います。
備忘録
- ガムテープと油性ペンがあると何かと役立つ。
- 硬化や乾燥待ちのために時間を把握しておく必要があるので、時計は必須。気温は硬化時間と関係するので、温度計もあった方が良い。
- 自分のドリルや工具にはテプラ等で名前を書いておく(クライミングギア以上に、同じような装備になるため)。
- ユマーリングは、右手アッセンダーから下げたアブミに左足で乗込む、というのが僕としては扱いやすかった。